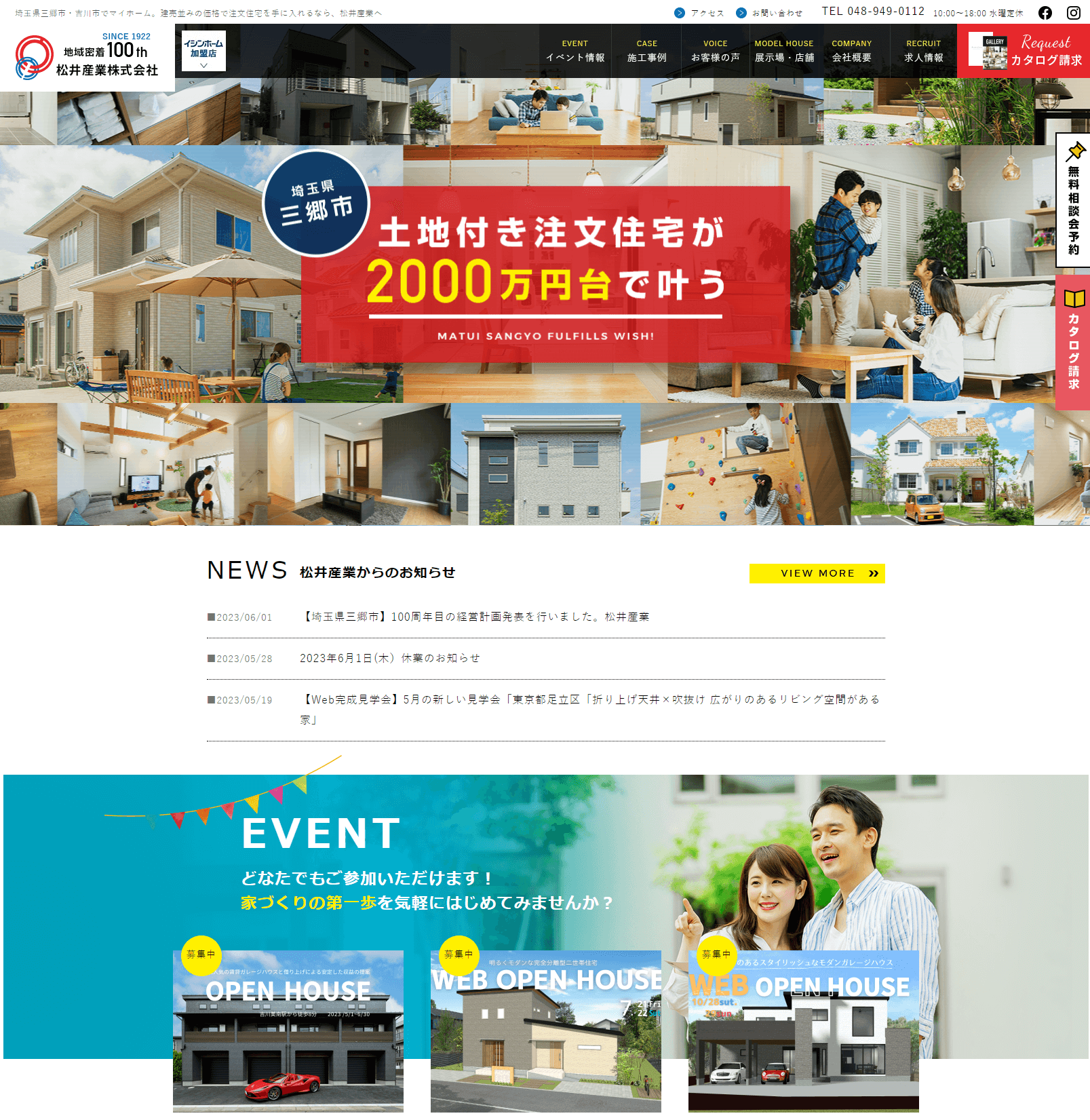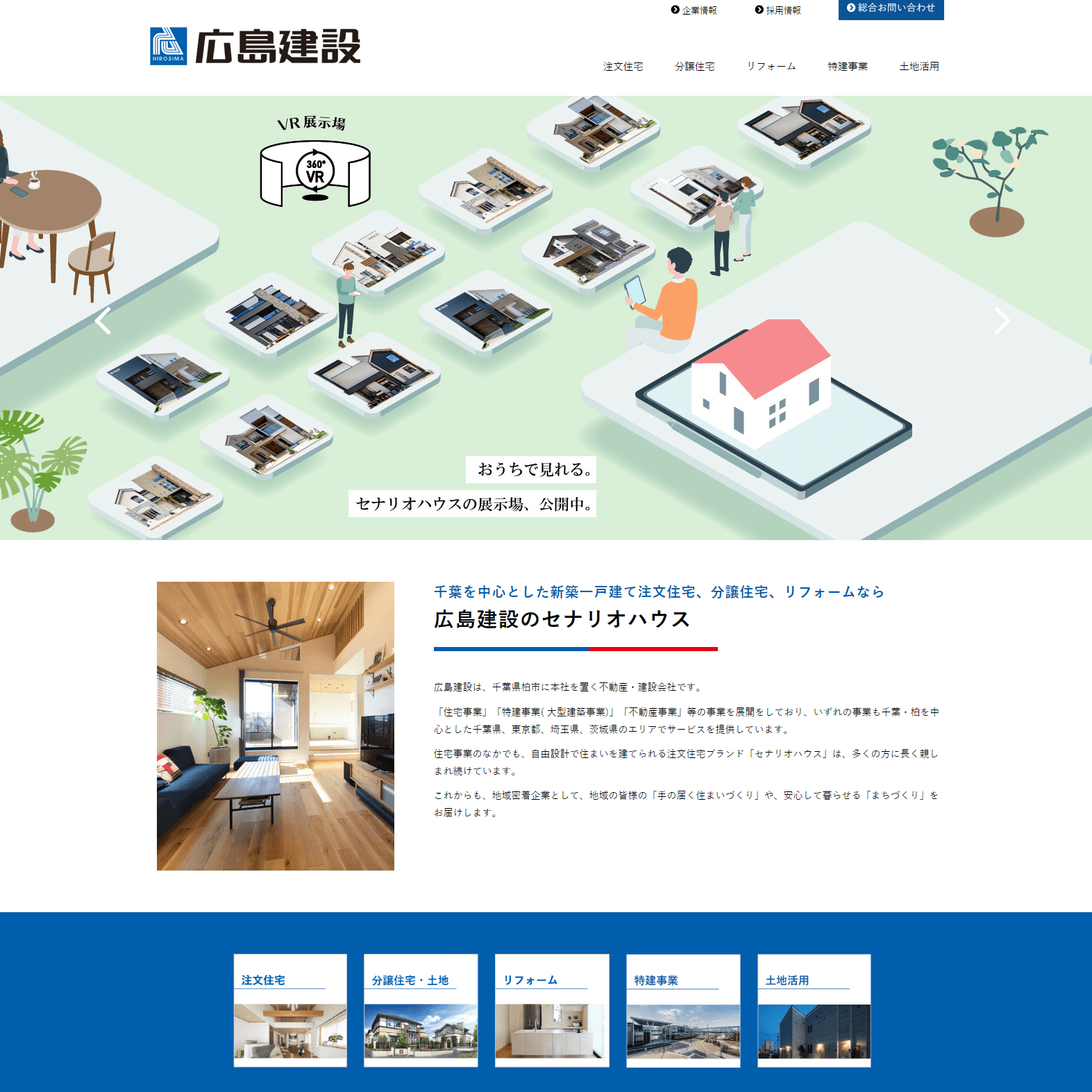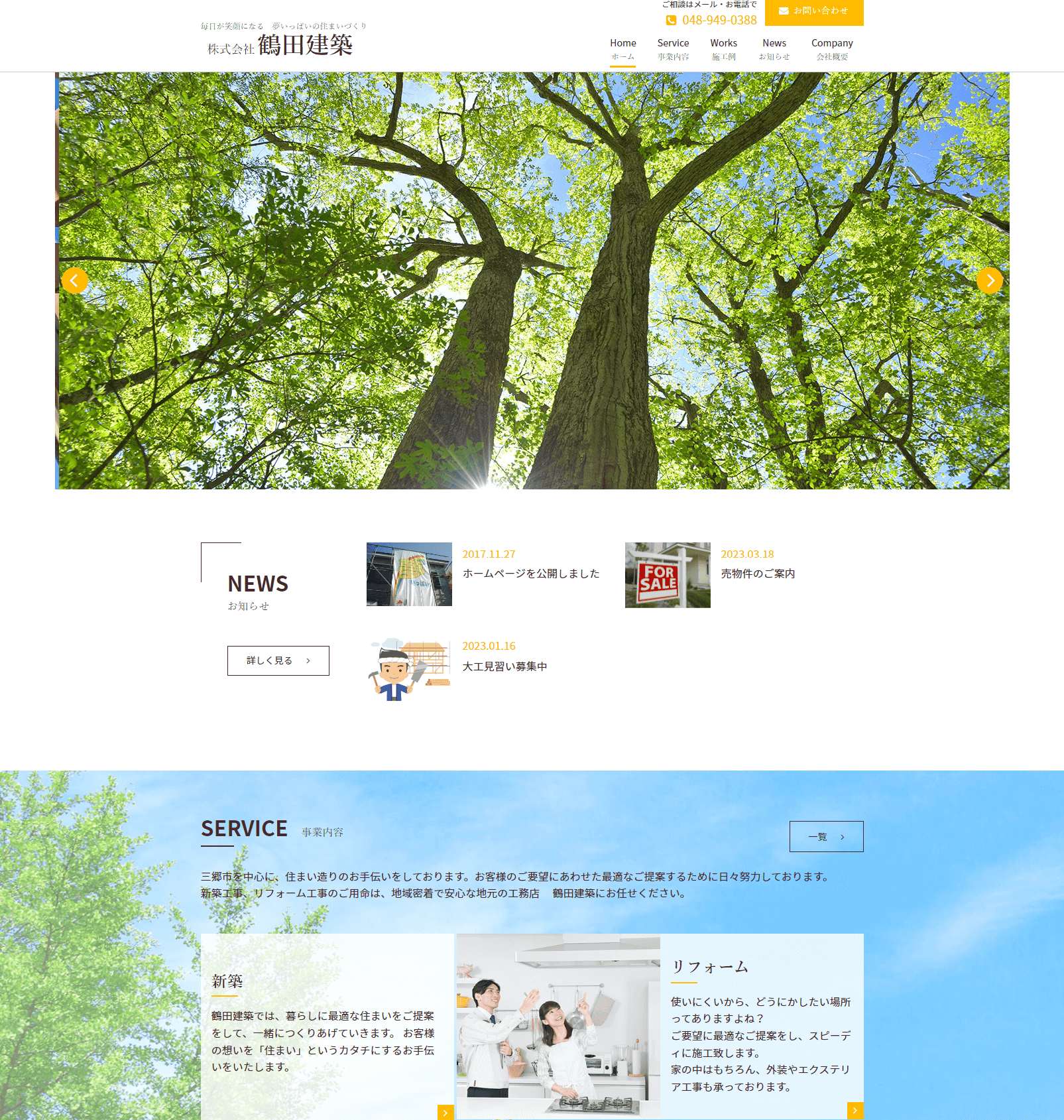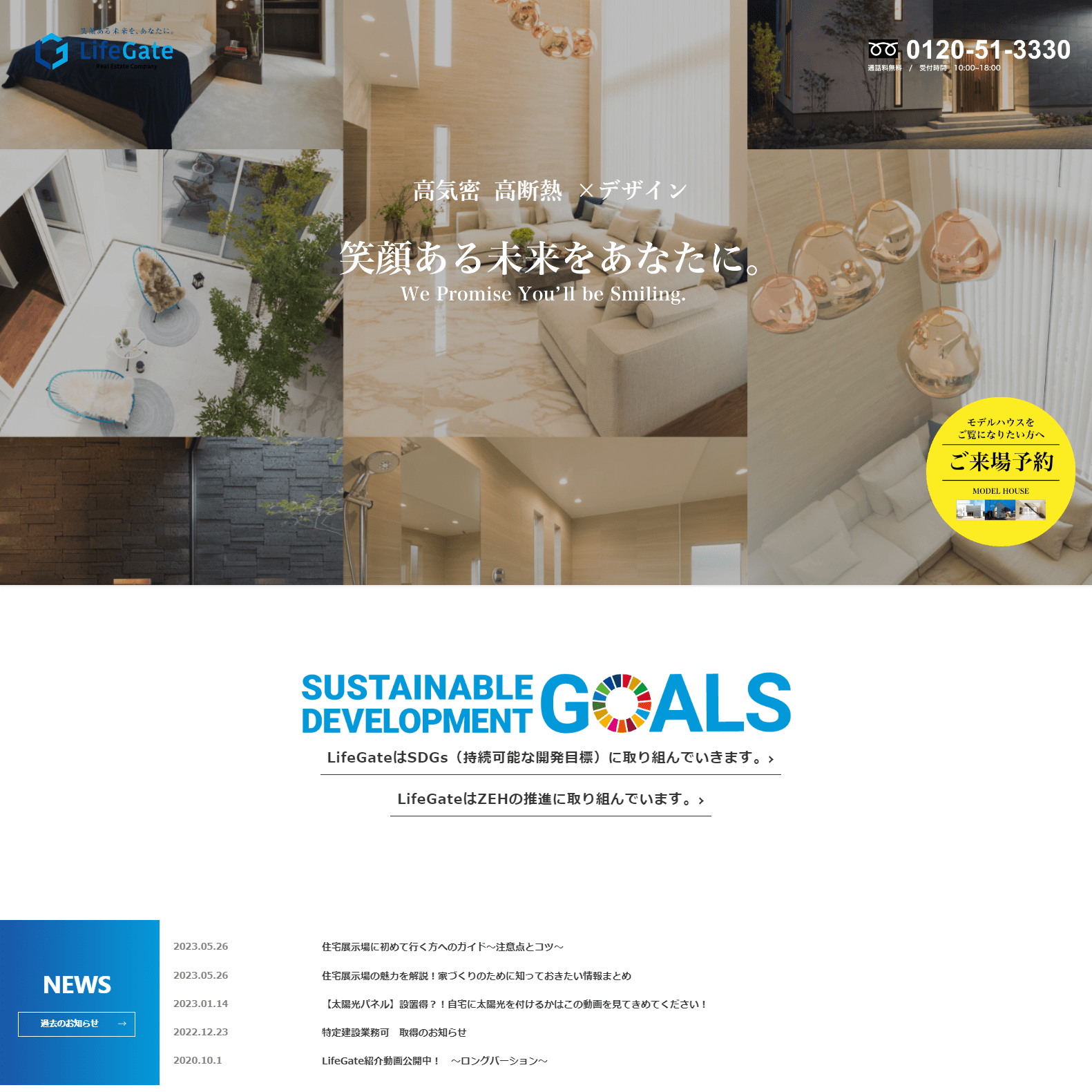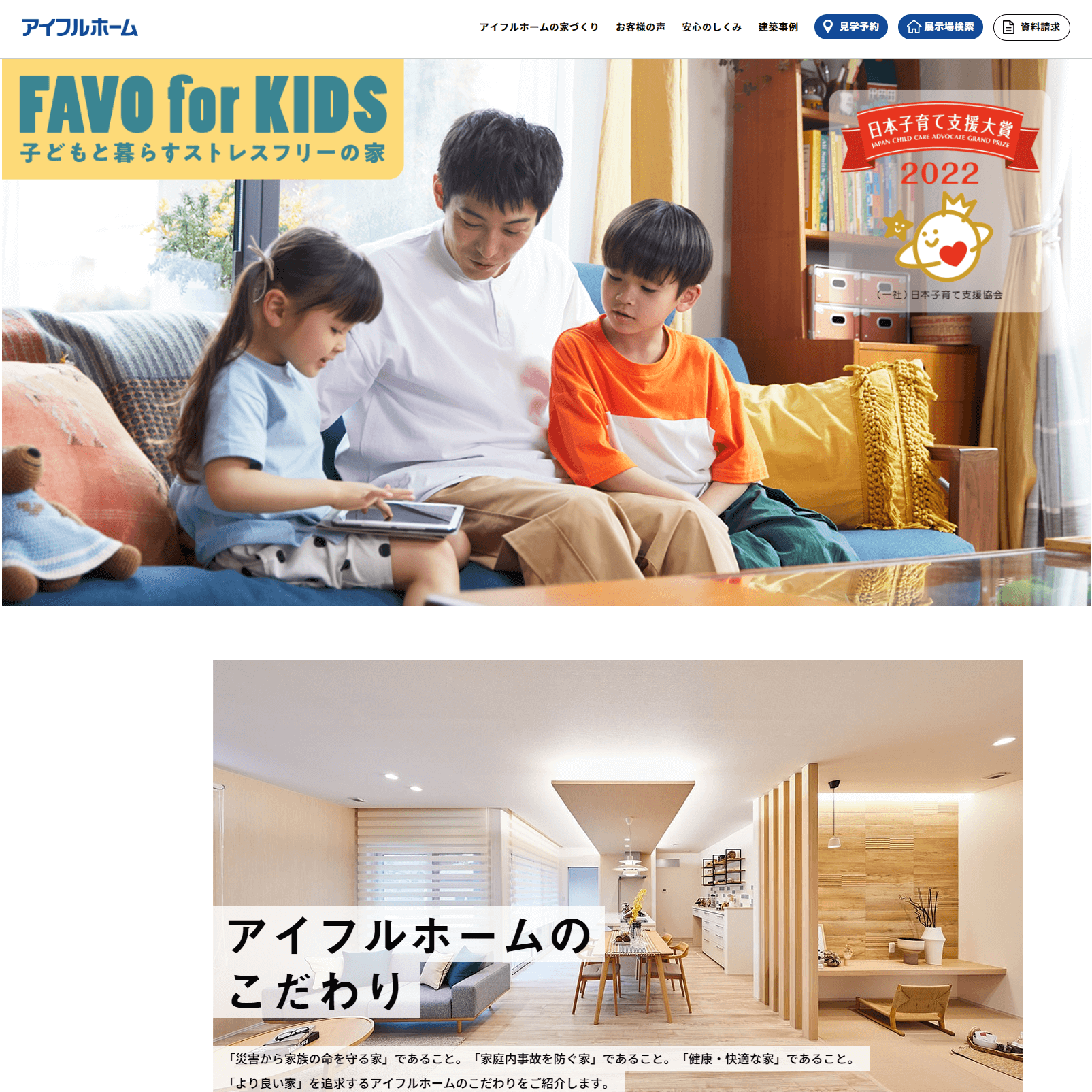高性能で環境にやさしいGX志向型住宅ですが、補助金を受けるには申請が必要になります。また、給付条件も決まっているため、すべてクリアしないと支給されません。そこで今回は、GX志向型住宅の補助金についてまとめてみました。申請期間や給付条件についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
CONTENTS
適合するともらえる補助金額と期間
GX志向型住宅は、従来のZEH基準を大きく上回る、高性能で環境にやさしい環境配慮型住宅です。光熱費の負担を軽減する効果が期待され、補助金制度も受けることができます。
ここでは、GX志向型住宅に適合した場合にもらえる補助金額と期間について解説します。
1戸あたり最大160万円
子育て世帯などに特化したZEH水準住宅や長期優良住宅とは違い、すべての世帯が交付の対象となります。金額は1戸あたり最大160万円、条件に付いては後述しますが、対象外となる地域・住宅もあるため注意が必要です。
ちなみに、ZEHは1戸あたり40万円、長期優良住宅は1戸あたり80万円が支給されます。それぞれ解体を含む場合は60万円・100万円と少し高くなります。
交付申請期間
補助金制度を利用するには、交付申請が必要です。
申請期間は2025年5月中旬~12月31日まで、予約期間は2025年5月中旬~11月14日までとなっており、予約期間とは、補助金の予算残額がゼロになる前に一定期間申請枠を確保しておくことを意味します。
申請期間内であっても、予算が上限に達すると申請が打ち切られるため、予算が底を尽きてしまう恐れがある方は予約枠を確保しておくと安心です。もちろん、申請期間を過ぎた場合も交付されません。
また「基礎工事後の工程の工事」へ着手する期間と完了報告機関も把握しておきたいところです。子育てグリーン住宅支援事業のホームページから予算残額(予算に対する補助金申請額の割合)が確認できるので、気になる方はチェックしてみてください。
対象外になる場合がある
補助金を受けるには、いくつかの条件をクリアする必要があり、さらに住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下でなければいけません。全世帯が補助金制度の対象となるのは大きなメリットですが、それ以外で対象外となってしまう場合があります。
まず、災害の警戒および危険に該当する区域です。「土砂災害特別警戒区域」や「災害危険区域」などが挙げられ、都市再生特別措置法の規定により当該住宅の届出をしたにも関わらず、勧告に従わなかった住宅も対象外となります。
次に「立地計画適正化区域内の居住誘導区域外」「災害レッドゾーン」です。災害レッドゾーンとは、地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域(浸水被害防止区域)、前述した災害危険区域・土砂災害特別警報区域を指します。
地域独自の補助金
国費が充当されていない地域独自の補助金であれば、併用が可能です。たとえば石川県の場合「住まいの省エネ促進事業費補助金」が2025年より実施されます。
ほかの地域も併用できる補助金があるので、各自治体のホームページで確認してみてください。
お得なのは補助金だけではない?
補助金の交付以外にも、室内の温度を一定に保ったり、結露の減少で耐久性がアップしたりなど、うれしいことがたくさんあります。また、断熱性が向上することで、光熱費も抑えられるでしょう。
家をよい状態に保てるため、住まいの資産価値が上がり、将来売却するときも役に立ちます。
GX志向型住宅に求められる条件
GX志向型住宅を建てるには、断熱等性能等級・一次エネルギー消費量・HEMS導入の3つの条件をクリアしなければいけません。
ここでは、それぞれの条件について詳しく解説します。
断熱等性能等級6以上
1つ目は、断熱等性能等級6以上です。断熱等性能等級とは、断熱性能を7つのランクに分類したもので、数字が大きいほど高断熱性能になります。
これまでは等級4が最高ランクとされていましたが、2022年4月・10月に等級5~7が追加されたことで、高断熱性能=等級6以上でなければ認められなくなりました。
ちなみにZEHや長期優良住宅は断熱等性能等級5が採用されています。十分な断熱性能ですが、GX志向型住宅はそれ以上の断熱性能を有しているというわけです。
一次エネルギー消費量の削減率
2つ目は、一次エネルギー消費量の削減率です。一次エネルギー消費量とは、一般家庭が消費するエネルギー量を意味します。
GX志向型住宅では、再生可能エネルギーの有無で削減率が変わり、含める場合は標準を上回る省エネ・創エネを達成する必要があります。そのため、削減率は100%以上です。
一方で再生可能エネルギーを含まない場合、削減率35%以上と低くなります。省エネ性能の高い住宅設備を採用し、35%以上の省エネ性能を満たさなければいけません。
太陽光発電などを活用することで、どれだけ一次エネルギー消費量を削減できるかが大きなポイントになるでしょう。
HEMSの導入
3つ目は、HEMS(高度エネルギーマネジメント)の導入です。家庭でのエネルギー使用状況をパソコンやスマホなどで確認できるシステムのことで、架電や電気設備の使用量を「見える化」するだけでなく、自動制御によって節約にもつながります。
GX志向型住宅に関する注意点
補助金は、一定の期間内に申請し、条件を満たすことで支給されます。しかし、条件を満たしていても、予算の上限に達すると申請が打ち切られるため注意が必要です。
ほかにも、以下の点に気をつけましょう。
床面積の補助要件
住宅の床面積は、50㎡以上240㎡以下でなければいけません。広すぎたり、小さすぎたりする住宅は原則で対象外となります。
また、床面積をクリアしていても、土砂災害特別警報区域や災害レッドゾーンなどの危険区域に建てる場合は適用されないので要注意です。
土地に関する情報は、不動産会社や専門家に相談してください。
グリーン住宅支援事業者に依頼する
「グリーン住宅支援事業者」に登録されたハウスメーカーのみ、補助金制度が利用できます。それ以外のハウスメーカーに依頼しても、補助金は受けられません。
デメリットを知っておく
補助金が受けられ、快適で安全な暮らしを実現してくれるGX志向型住宅ですが、デメリットも存在します。建てたあとに失敗しないように、事前にきちんと確認しておきましょう。
主なデメリットは以下のとおりです。
1つ目は、初期コストがかかりやすい点です。そもそも、性能が高い住宅は費用が高く、どうしてもハイコストになりがちです。GX志向型住宅の場合も、太陽光発電やHEMSなどの導入が必要になるため、初期コストは高くなるでしょう。
その代わり、国や地域の補助金が受けられるのは大きなメリットです。賢く活用することでコストを抑えることができます。
2つ目は、太陽光パネルの設置が必要になる点です。先ほども述べましたが、GX志向型住宅は太陽光発電やHEMSの導入が求められるため、設置なしでは建築できません。
また、設置した場合でも、日照条件や屋根の形状などによって発電効率が悪くなったり、定期的なメンテナンスや交換が必要になります。
再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量を100%以上削減できるのはメリットですが、立地条件なども含めて検討しなければいけません。
3つ目は、設計や施工がむずかしい点です。高断熱性能や省エネ技術を活用するため、設計・施工に手間と時間がかかります。だからといって、安さだけでハウスメーカーを選んでしまうと失敗します。
かならず施工実績があり、専門性の高いハウスメーカーに依頼しましょう。
まとめ
GX志向型住宅の補助金について、申請期間や給付条件などを紹介しました。ZEHや長期優良住宅を上回る省エネ・創エネを有すGX志向型住宅は、将来性があり、安心で快適です。条件を満たすと補助金も受けられるので、高くて諦めている方も、負担を軽減して建てることができます。一方で、予算の上限に達すると申請が打ち切られたり、補助金対象外の地域があったりなど、デメリットも存在します。給付条件もあるため、建築を検討している方は事前に確認してから家を建てましょう。